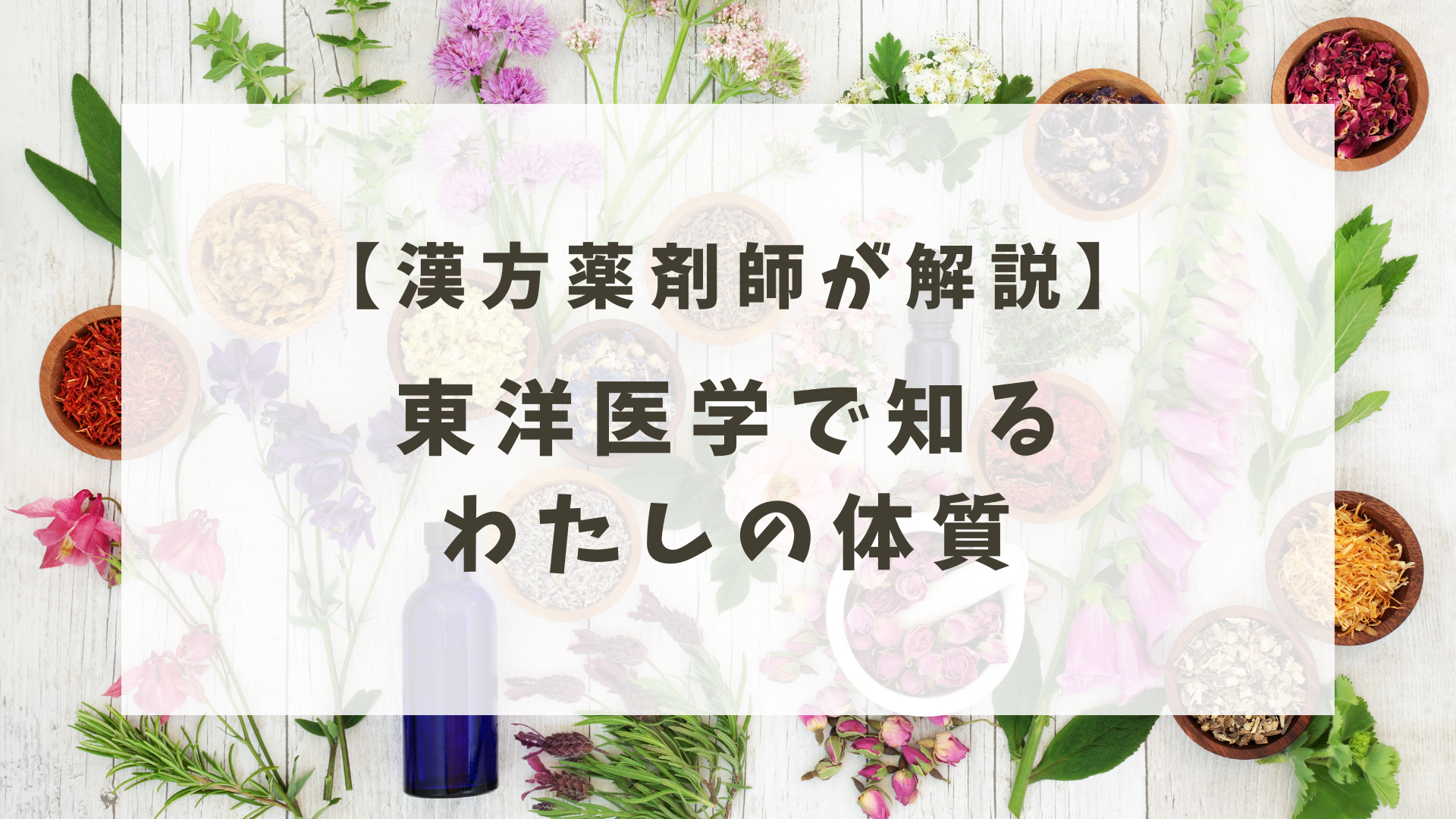【保存版】東洋医学における体質別セルフケア完全ガイド
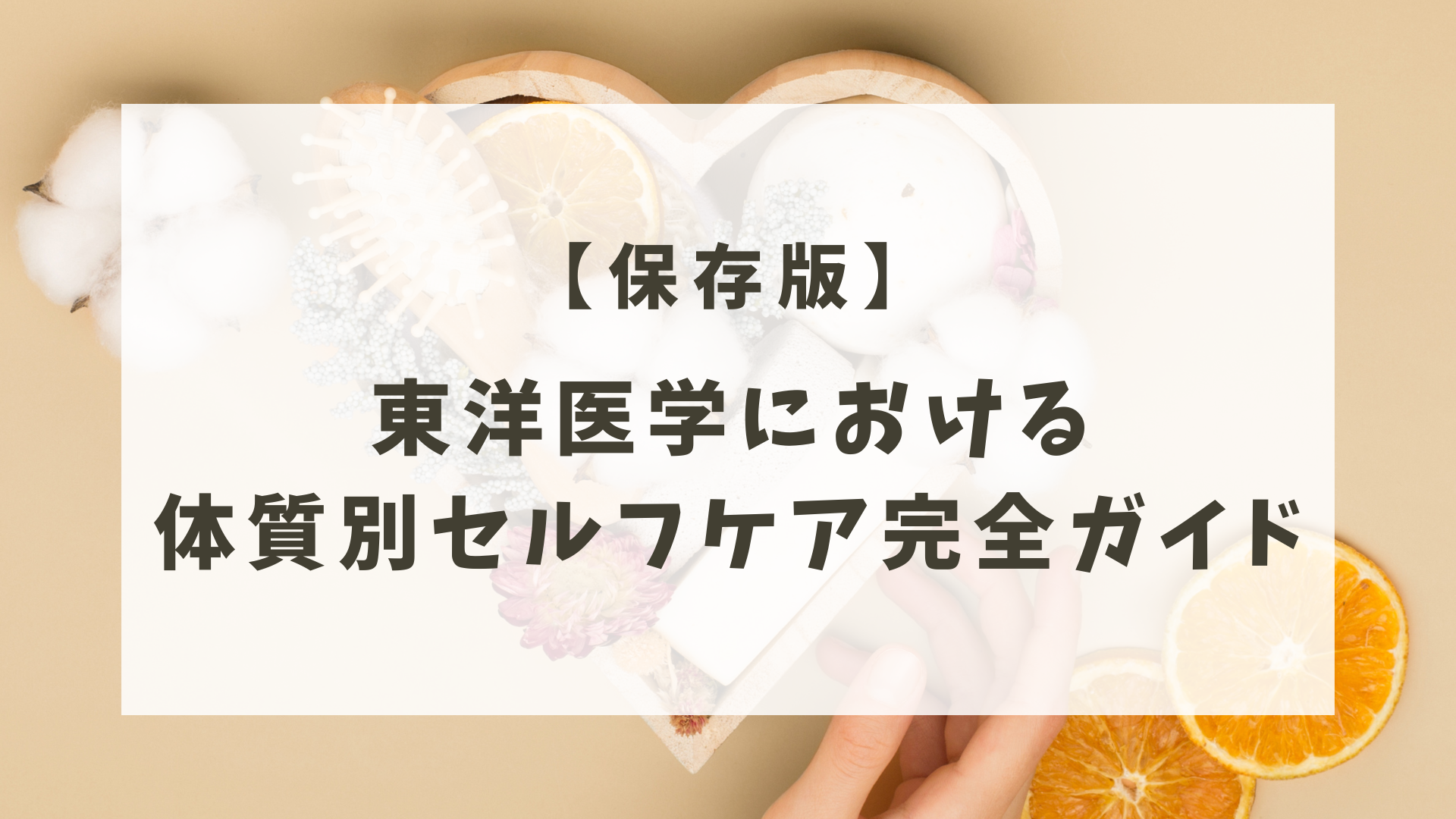
肩こりや疲れを改善しようと色々試してみたけど、あまり効果を感じられなかった……。
そんな経験はありませんか?
東洋医学では、人それぞれの不調や悩みは「体質」と深く関わっていると考えます。
同じ症状でも、原因や必要なケアは人によって異なります。
つまり、自分の体質に合ったセルフケアこそが、体や心の不調を和らげ、毎日を快適に過ごすための近道になるのです。
本記事では、東洋医学の基本である「気・血・水」の考え方に沿った体質別の特徴とおすすめのセルフケア方法を、わかりやすく解説します。
取り入れたい食材や生活習慣など、今日から取り入れられるヒントをまとめました。

前回の「体質チェック」をまだ行っていない方は、下記リンクより今の自分の体質を把握してから読み進めると、よりスムーズです。
目次
東洋医学で考える「体質別セルフケア」とは
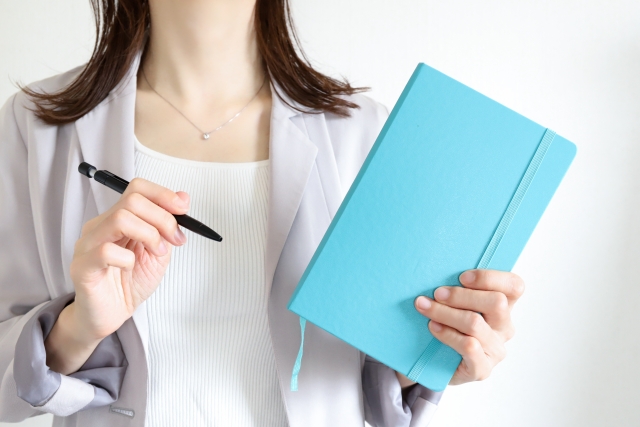
頭痛や肩こり、生理痛など、たとえ同じ不調でも、原因は人によって異なります。この違いが、東洋医学における「体質」です。
体質が違えば、必要なケアも変わってきます。
ここでは、体質別セルフケアの基本的な考え方と、なぜ“自分に合った”方法を選ぶことが大切なのかを解説します。
体質別セルフケアの基本的な考え方
東洋医学では、人の体質を「気・血・水(き・けつ・すい)」という3つの要素のバランスで捉えます。[1]
健康な状態ではこの3つが過不足なく調和していますが、食べ物や生活習慣、その日の体調などによってバランスが崩れると、不調が現れやすくなります。

たとえば気が不足している人では、多くの場合、
・疲れやすい
・風邪をひきやすい
・下痢をしやすい
などの不調が見られるでしょう。
体質別セルフケアの目的は、このバランスの乱れを整えることです。
足りないものは補い、滞ったものは流し、余分なものは取り除く。
このシンプルな考え方をベースに、食事・運動・休養の取り方を自分のタイプに合わせることで、不調を根本から改善しやすくなるのです。
なぜ体質に合わせたケアが大事なの?
東洋医学の基本概念に「同病異治(どうびょういち)」というものがあります。[2]
これは「同じ症状でも、原因や背景が異なれば治し方も異なる」という意味です。

同じ“頭痛”でも、血の流れが悪いタイプと、余分な水分が溜まっているタイプとでは、取るべきアプローチが違います。
体質に合ったケアを選ぶことで、回復力が高まり、改善が早くなります。
逆に体質を無視したケアは効果が出にくく、“やっているのに変わらない”という結果になりかねません。
体質に合わないケアは逆効果になることも……
東洋医学には「虚実(きょじつ)」という考え方があります。[2]
虚は不足している状態、実は過剰や滞りがある状態です。
不足している人がさらに消耗するケアをしたり、滞っている人が過剰に補うケアをしたりすると、不調は良くなるばかりか悪化してしまいます。

たとえば、気が不足している人がハードな運動を続けると、さらにエネルギーを消耗して動けなくなるでしょう。
つまり、“体に良い”とされる方法も、体質に合わなければ逆効果になることがあるのです。
だからこそまず自分の体質を知り、それに合った方法を選ぶことが大切です。
気・血・水タイプ別のセルフケア

体質によって、適したセルフケアの方法は異なります。
ここでは、「気・血・水」の体質タイプ別に、日常生活で簡単にできるセルフケアのポイントをご紹介します。

“なんとなく調子が悪い”と感じている方も、自分に合った方法で心身を整え、毎日をより快適に過ごしましょう。
気虚タイプ
気の量が不足していて、やる気が出ず疲れやすく、免疫力も低下しています。
エネルギーを消耗しすぎないようにすることと、胃腸に負担をかけないことが重要です。[3]
| 生活上のポイント | おすすめの食材 |
| ・睡眠を十分にとって、休む。 ・激しい運動ではなく、基礎体力をつける運動を。 ・長風呂やサウナは、汗とともに気が流れてしまうため、じわっと汗が出てきたところでストップ。 ・食材は柔らかくしたり温かくしたりして、消化を助ける。 | ・米・芋類(さつまいも、じゃがいも、山芋) ・とうもろこし ・豆類(大豆、枝豆) ・きのこ類(しいたけ、舞茸) ・鶏肉 ・NG:冷たいもの、油っぽいもの、甘いもの |
気滞タイプ
気の流れが滞り、イライラしたり憂鬱や不安を感じやすかったりと精神的に不安定になりやすい状態です。
香りで気の流れを促し、ストレスを溜めないようにしましょう。[3]
| 生活上のポイント | おすすめの食材 |
| ・汗をかくくらいの運動をして気分転換をする。 ・体を締め付けないゆるやかな服装や髪型を意識する。 ・柑橘類などのアロマや入浴剤で気持ちをスッキリさせる。 ・深呼吸をする。 | ・柑橘類(グレープフルーツ、みかん、オレンジ) ・香り食材(春菊、セロリ、にら、大葉、茗荷) ・NG:大量の飲酒、にんにくや香辛料など辛味の食材 |
血虚タイプ
体内の血が不足していて、めまいや動悸、不眠などのトラブルを起こしやすくなります。
血をしっかり作ることと消耗しすぎないことが重要です。[3]
| 生活上のポイント | おすすめの食材 |
| ・偏食や、ダイエットなどで食事量を減らすことは控える。 ・運動は軽いウォーキング程度にする。 ・目の使いすぎは血を消耗するので、目を休める。スマホを見過ぎない。 ・血が作られる23時には寝る。 | ・小松菜、ほうれん草、人参 ・卵 ・青魚、鮭、ぶり ・黒いもの(黒米、黒豆、黒ごま、ひじき) ・プルーン ・NG:冷たいもの、油っぽいもの、甘いもの |
瘀血タイプ
血の流れが悪いことで関節痛や手足の冷えが出やすく、とくに血が滞っているところでは刺すような痛みが出ることがあります。
血流を改善するような生活習慣を意識しましょう。[3]
| 生活上のポイント | おすすめの食材 |
| ・ウォーキングやストレッチなど、適度な運動をする。 ・同じ姿勢が続くときは、適宜、体を動かすようにする。 ・湯船にゆっくり浸かる。 ・とくに下半身を温めるよう意識する。 | ・ネギ類(ネギ、玉ねぎ) ・おくら ・納豆 ・青魚、鮭 ・NG:冷たいもの、油っぽいもの |
陰虚タイプ
体の中の水分が不足し、潤いが足りない状態です。
汗をかきすぎないよう注意しましょう。[3]
| 生活上のポイント | おすすめの食材 |
| ・汗を大量にかくような運動、ホットヨガ、サウナなどは控える。 ・潤いが作られる23時には寝る。 ・加湿器を使う。 | ・水分の多い野菜(レンコン、トマト、冬瓜) ・梨、りんご ・豆腐、豆乳 ・牛乳、ヨーグルト ・豚肉 ・NG:辛いもの |
痰湿タイプ
体に余分な水分が溜まっている状態です。
水分代謝を改善し、余分な水分を体の外に出すことが重要です。[3]
| 生活上のポイント | おすすめの食材 |
| ・運動や半身浴などで発汗を高める。 ・暴飲暴食や多量のアルコールは、余分な水分を増やすので控える。 ・水分は少しずつ摂るよう意識する。 | ・豆類(小豆、大豆、黒豆、緑豆もやし) ・とうもろこし ・海藻類(昆布、ひじき、わかめ) ・ウーロン茶、プーアル茶、ハト麦茶 ・NG:冷たいもの、油っぽいもの、甘いもの |
体質別セルフケアを続けるコツ

自分に合ったセルフケアを見つけても、続けられなければ効果は実感しにくいものです。

また、体の状態は日々変化しているため、同じ方法がずっと最適とは限りません。
ここでは、体質別セルフケアを無理なく続け、効果を高めるためのポイントを3つご紹介します。
1つだけ習慣化する
セルフケアは、あれもこれも一度に取り入れようとすると、続けるのが難しくなります。
まずは、自分のタイプに合ったケアの中から“これならできそう”と思えるものを1つだけ選びましょう。
たとえば、おすすめ食材を1つスーパーで探してみる、夜は湯船につかる、23時までに寝るなど、小さな習慣で構いません。成功体験を積み重ねることで、無理なく習慣になっていきます。
体質の変化に目を向ける
体質は一生同じではなく、季節や年齢、生活環境などによって変化します。女性は、生理周期によっても揺らぎやすいでしょう。加齢に伴い、気や血が不足しやすくなることもあります。
“前は効果があった方法が合わなくなった”と感じたら、今の自分の状態に合わせてケアを見直しましょう。
不調が長引くときは専門家に相談する
セルフケアはあくまで日常のサポートであり、すべての不調を解決できるわけではありません。とくに、不調が長引く、悪化している、原因がわからないといった場合は、早めに医療機関を受診して専門家に相談しましょう。
適切な診断や治療を受けながらセルフケアを続けることで、より安全で効果的に体調を整えられます。
体質に合ったセルフケアで健康に過ごそう

本やネットで話題になっている健康法は数えきれないほどありますが、大切なのは“自分の体質に合っているかどうか”です。
東洋医学の考え方を取り入れることで、自分に必要なケアと望ましくないケアを見分けやすくなります。
今回ご紹介した方法を、 まずは無理のない範囲で始め、体の変化を感じながら続けてみましょう。

“前より調子が良い”と感じられる時間を少しずつ増やしていくことが、心身の健康につながります。
自分に合ったケアを知り、毎日の暮らしに取り入れながら、軽やかで心地良い毎日を過ごしていきましょう。